コラム
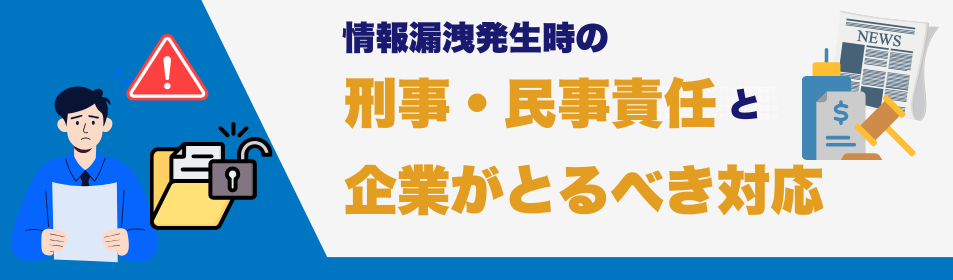
情報漏洩発生時の刑事・民事責任と企業が取るべき対応策
情報漏洩発生時のリスクとは
もし情報漏洩が発生した場合に、どのような法的責任が問われるか、明確に把握できているでしょうか。
情報漏洩は単なるデータの流出ではなく、顧客や取引先との信頼関係を損ねる重大な事件です。さらに、発生後の対応が適切でなければ、企業は刑事責任や民事責任を負う可能性があり、場合によっては行政処分や社会的信用の失墜に直結するリスクもあります。
近年、内部不正や外部からの不正アクセスによる個人情報や機密情報の漏洩が増加傾向にあります。情報漏洩の影響は、単に漏洩したデータそのものに留まらず、株主・取引先・顧客への説明責任やメディア対応、さらには訴訟対応など多岐にわたります。
本コラムでは、漏洩発生時に企業が直面する可能性のある法的責任を整理し、実務上の対応策を具体的に解説します。
目次
1.情報漏洩発生時に企業が直面する法的責任とは
情報漏洩が発生すると、企業は以下のような法的責任に直面する可能性があります。
- 刑事責任
個人情報保護法や不正競争防止法などの違反により、法人としての罰金や役員個人の刑事責任が問われる場合があります。 - 民事責任
漏洩した情報により第三者に損害が生じた場合、損害賠償請求を受ける可能性があります。 - 行政責任
個人情報保護委員会や経済産業省などの監督官庁からの指導や命令、場合によっては業務停止命令などの行政処分を受けることがあります。

2.刑事責任:個人情報保護法違反と不正競争防止法違反
前章で述べたように、企業は情報漏洩発生時には刑事責任を負う可能性があります。ここでは具体的に、個人情報保護法と不正競争防止法の観点から説明します。
個人情報保護法違反
個人情報の保護に関する法律では、個人情報を不正に取得・提供した場合や、業務上知り得た秘密を漏らした場合に刑事罰が科されます。例えば、顧客の住所や生年月日などの情報を業務外で第三者に不正提供した場合、個人は最大1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となります。
さらに、その行為が法人の業務に関連して行われた場合には、行為者本人の処罰に加え、法人にも1億円以下の罰金が科されます。対象となるのは従業員に限らず、法人の代表者や代理人なども含まれます。
[個人情報保護に関する法律 (第176条~第185条) ]
不正競争防止法違反
営業秘密情報を不正に取得・使用等の行為をした場合、不正競争防止法違反となります。刑事罰として最大10年の懲役または2,000万円以下の罰金(海外使用等は3,000万円以下)が科される可能性があります。
また、法人の代表者や従業員などが法人の業務に関連してこれらの違反行為を行った場合には、行為者本人に加えて、法人にも罰金刑が科されることがあります。
[不正競争防止法 (第21条~第22条)]
このように、個人情報保護法や不正競争防止法では、情報漏洩や営業秘密の不正取得・使用等の行為が明確に刑事責任の対象とされています。そしてこれらの行為は、企業や第三者に損害を与える場合には民事上の損害賠償責任にも直結します。次章では、民事責任について詳しく整理します。
3.民事責任:債務不履行責任と不法行為責任
前章で整理した刑事責任に加えて、情報漏洩によって第三者に損害が生じた場合、企業は民事責任も問われることがあります。具体的には、契約上の義務違反に基づく債務不履行責任や、不法行為に基づく損害賠償責任が該当します。
債務不履行責任
企業は契約上、顧客や取引先に対して個人情報を適切に管理する義務を負っています。たとえば、契約書に「顧客情報の保護を行う」と明記されている場合、この義務を怠ると債務不履行として損害賠償請求の対象になります。
[民法(第415条)]
不法行為責任
企業や従業員が故意または過失により他者の権利・利益を侵害した場合、不法行為責任が発生します。たとえば、顧客情報の漏洩によってなりすましや金銭被害が発生すると、企業は損害賠償責任を負う可能性があります。
[民法(第709条)]
民事責任を正しく理解することは、企業に求められる情報管理体制の重要性を再認識する契機となります。契約上の義務や不法行為に基づく責任を把握し、適切な対策を講じることで、損害の拡大防止や企業の信頼維持につなげることが可能です。

4. 行政責任:個人情報保護法に基づく報告義務と企業の対応
第2~3章では、刑事責任と民事責任について整理しました。本章では、情報漏洩時の行政責任に焦点を当て、行政対応や報告義務について詳しく解説します。
情報漏洩が発生した場合、企業は個人情報の保護に関する法律に基づき、速やかに個人情報保護委員会(PPC)に報告する義務があります。報告義務を怠ると、行政指導や勧告、改善命令などの行政処分が科される可能性があり、社会的信用の低下や法的リスクの増大につながります。
報告の種類と期限
- 速報
発覚日から3〜5日以内に提出 - 確報
発覚日から30日以内に、漏洩の詳細や対応状況を報告
※不正な目的で行われたおそれがある場合は、発覚日から60日以内に確報を提出
報告に含める主な情報
- 漏洩等の発生日時
- 漏洩等の概要
- 漏洩等により影響を受けた個人の数
- 漏洩等の原因
- 再発防止策
- その他、個人情報保護委員会が必要と認める事項
報告方法や様式についての詳細は、個人情報保護委員会の公式ウェブサイトで確認できます。
行政処分の可能性
個人情報保護法違反や報告義務違反が認められた場合、個人情報保護委員会は次のような措置を取る可能性があります。
- 助言・指導
違反行為の是正を求める助言や指導 - 勧告
違反行為の停止や改善を求める勧告 - 命令
違反行為の是正や再発防止措置を命じる行政命令 - 公表
企業名や違反内容の公表
これらの勧告や命令に従わない場合、刑事罰が科される可能性があります。
[個人情報保護に関する法律]
5.初動対応のフローと社内体制の整備
前章までで、情報漏洩発生時に企業が直面する刑事・民事・行政上の責任について解説しました。これらの責任を踏まえ、実際に情報漏洩が発生した場合には、迅速かつ的確な初動対応が求められます。本章では、その対応フローと社内体制の整備について 説明します。
基本的なフローは次の通りです。
- 漏洩事実の確認
ログ解析や関係者へのヒアリングで、漏洩の有無と範囲を特定します。 - 影響範囲の特定
漏洩対象の情報や影響を受ける顧客・取引先を洗い出します。 - 被害者への通知
必要に応じて、漏洩事実と対応策を通知します。 - 行政報告
個人情報保護委員会や所管省庁への報告を行います。 - 再発防止策の実施
アクセス権限見直し、教育訓練、システム改善などを行います。
社内体制としては、情報漏洩対応マニュアルの策定や初動対応チームの設置が重要です。刑事・民事・行政責任の整理を踏まえ、役員やマネージャが中心となり迅速な意思決定と情報共有を行うことで、被害を最小限に抑えることが可能です。
情報漏洩発生時の対応についての詳細は、以下のコラムをご参照ください。

6.情報漏洩についての公表・通知の留意点
情報漏洩が発生した際の公表や通知は、企業の信頼性を保つために重要な要素です。しかし、適切な対応をしないと、さらなる信頼失墜や法的リスクを招く可能性があります。
公表や通知に際しての留意点としては、以下のような点が挙げられます。
- 正確性の確保
事実確認を徹底し、誤情報を伝えない。 - 過剰表現の回避
漏洩規模や影響範囲を誇張せず、正確に伝える。 - 過剰表現の回避
漏洩規模や影響範囲を誇張せず、正確に伝える。 - 説明ポイントの明確化
漏洩原因、影響範囲、対応策、再発防止策を整理し、関係者に分かりやすく説明する。
公表・通知を適切に行うことで、顧客や株主の信頼回復につながります。また、問い合わせ窓口を設置し、迅速かつ適切に対応することが重要です。
7. まとめ:情報漏洩発生時に取るべき対応と責任
情報漏洩は、企業にとって法的責任と社会的信用の両面で大きなリスクを伴います。
企業は、刑事・民事・行政責任の整理を行い、初動対応フローと社内体制を整備することが不可欠です。漏洩発生時の迅速な対応、正確な公表・通知、再発防止策の実施により、リスクを最小限に抑え、信頼回復を図ることが可能です。
また、役員・管理者の善管注意義務や委託先管理の重要性を認識し、情報セキュリティポリシーの継続的な見直しや従業員教育を実施することで、長期的な情報漏洩リスクの軽減につなげることができます。
出典・参考情報(2025年8月時点)
本コラムは2025年7月時点の資料および法令を参考に執筆しています。リンク切れや法改正が発生する可能性があるため、最新情報については各機関の公式サイトをご確認ください。
参考リンク
- 個人情報保護委員会:https://www.ppc.go.jp/
- 経済産業省:https://www.meti.go.jp/
- e-Gov 法令検索:https://laws.e-gov.go.jp/
お問合せ
BlackBox Suiteは、多くの実績を持つ情報漏洩対策ソリューションです。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
利用用途やリスクに応じて、最適なご提案をいたします。