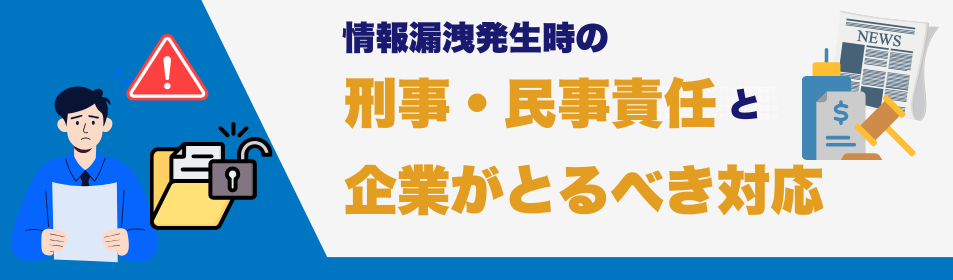コラム

医療業界の個人情報保護と情報漏洩防止対策の実務
医療業界での情報漏洩リスク
病院やクリニックといった医療機関では、日々膨大な量の患者情報を取り扱っています。診療記録、検査データ、投薬履歴、保険情報といった情報は、患者の健康や生活に直結する極めてセンシティブな個人情報です。こうした情報は、漏洩や不正利用が起きれば患者のプライバシーや信用を損なうだけでなく、医療機関そのものの信頼性にも深刻な影響を与えます。
医療分野における情報保護の重要性は、単に法令順守にとどまりません。患者が安心して診療を受けられる環境を維持するための基盤であり、医療機関の社会的責任そのものでもあります。では、実際に医療現場で個人情報を安全に管理し、情報漏洩を防ぐためにはどのような体制や実務的取り組みが必要なのでしょうか。
本コラムでは、実際に発生した漏洩事例やガイドラインに基づき、医療機関が講じるべき体制整備、安全管理措置、そして漏洩時の対応や監査準備に至るまでを整理し、実務的な視点から情報漏洩防止策を解説します。
目次
1.医療業界における情報漏洩の実例
医療機関では個人情報の取り扱いが日常的に行われているため、情報漏洩のリスクは常に存在します。診療記録や検査データ、投薬履歴、保険情報など、患者の健康や生活に直結する情報が漏洩すれば、プライバシーや信用に深刻な影響を与えるだけでなく、医療機関の信頼にも関わります。以下は実際に発生した事例です。
職員がSNSに患者のカルテ写真を投稿した事例
職員が患者のカルテ写真をSNSに投稿し、個人情報が漏洩する事案が発生しました。外部からの指摘により当日中に削除されたものの、約1カ月間閲覧可能な状態となっていたようです。
この事案を受け、院内では、全職員への個人情報管理の周知徹底や、個人情報保護研修・採用職員オリエンテーションでの事例共有などが、再発防止策として挙げられています。
出典:仙台市立病院「市立病院における個人情報漏洩について」
https://hospital.city.sendai.jp/customer/kisyahappyou.html
元教授が患者情報を不正持出しした事例
元教授が在職中に知り得た患者情報を不正に持ち出し、大学退職後に、アンケート及び自身が開設したクリニックの紹介の書面を、当該患者さん宛に郵送していることが判明しました。
本件を受けて、大学および院内では、アクセス権限の管理と監視体制の強化、職員教育の徹底が実施されました。また、法令に基づく関係機関への報告、外部弁護士を加えた事実関係調査、院内での個人情報取扱いに関する再度の注意喚起などの措置が講じられました。
出典:広島大学病院「 (お詫び)元教授による患者情報の目的外利用について」
https://www.hiroshima-u.ac.jp/hosp/news/85682
これらの事例から明らかなように、医療情報漏洩の原因は外部からの不正アクセスだけではありません。職員の不適切な取扱いや内部管理体制の不備といった内部リスクも大きな割合を占めているのです。
次章では、こうしたリスクに対応するために求められる情報管理体制について解説します。

2.医療業界で求められる情報管理体制の概要
個人情報の取り扱いにおけるリスクを最小化するため、医療機関には組織的な管理体制の構築が求められます。
個人情報保護委員会および厚生労働省が示す「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」では、医療機関が整備すべき体制のポイントが示されています。
情報管理体制の主な要素は以下の通りです。
- 個人情報の取扱い
適法かつ適正な方法で情報を取得・利用し、漏洩・滅失・毀損を防止するための措置を講じる必要があります。利用目的は特定し、原則として本人への通知または公表が求められます。 - 責任体制の明確化
個人情報保護を推進するため、専門的知識を有する管理者や組織体制を設け、規則策定や安全管理措置の立案・実施の必要があります。 - 管理者・委員会の設置
個人情報保護に関し十分な知識を有する管理者や監督者(例:役員など組織横断的に監督可能な者)を定めるほか、必要に応じて個人情報保護推進のための部署や委員会を設置することが求められます。 - 報告・連絡体制の整備
個人データの漏洩等の事故が発生した場合、または発生の可能性が高いと判断された場合には、責任者への報告や連絡を行う体制を整備する必要があります。外部からの苦情や相談への対応体制との連携も求められます。
出典:個人情報保護委員会・厚生労働省
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/01_iryoukaigo_guidance9.pdf
こうした情報管理体制を構築することで、職員による不適切な取り扱いや管理体制の不備といった内部リスクに対応できる基盤が整います。
次の章では、具体的な安全管理措置や従業者・委託先の監督について整理します。
3.安全管理措置、従業者の監督及び委託先の監督
情報管理体制を実効性のあるものとするためには、安全管理措置の具体化と従業者・委託先に対する監督が不可欠です。
ガイダンスでは、以下のような対応が求められています。
- 安全管理措置の実施
– 組織的措置:規程の策定、内部監査の実施、責任者の明確化など
– 人的措置:従業者に対する教育・研修、リスク意識の向上
– 物理的措置:施錠管理、入退室制御、紙媒体や端末の管理
– 技術的措置:アクセス権限の管理、アクセスログの保存、認証機能の活用 - 従業者の監督
– 権限や責任範囲の明確化
– 定期的な教育・研修
– 違反や疑わしい行為に対する確認・対応体制の整備 - 委託先の監督
– 契約書に情報の利用目的や安全管理措置の内容を明記
– 委託先が契約通りに適切な管理を行っているかの定期的な確認・監査
– 必要に応じた、改善指示や契約見直し
こうした施策により、日常業務で生じ得るリスクを抑制することができます。
次章では、万が一漏洩が発生した場合に必要な対応を整理します。
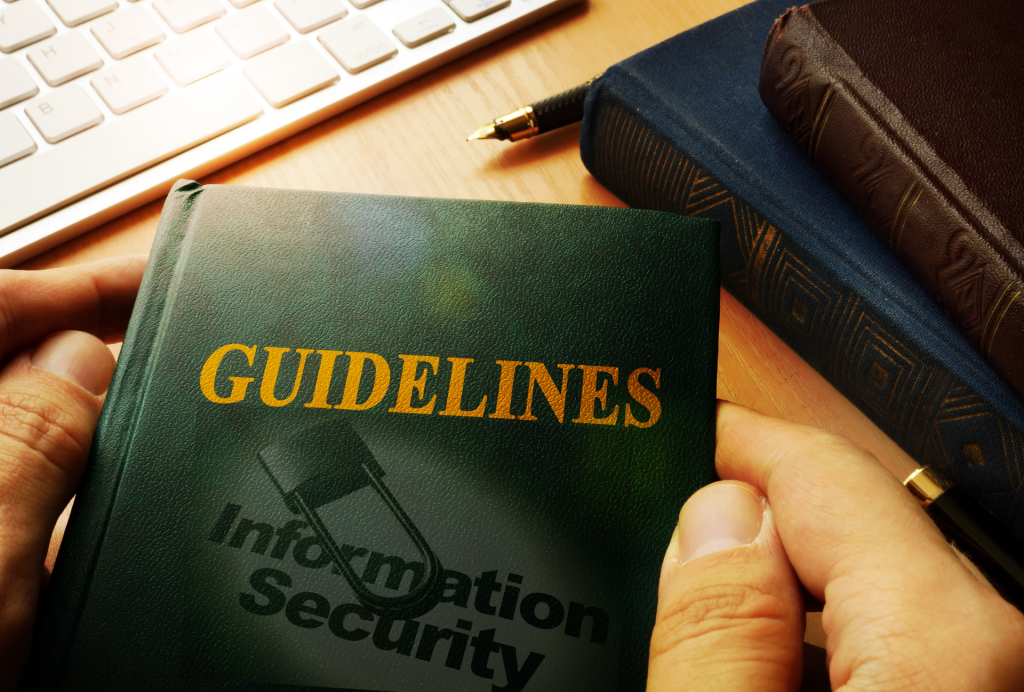
4. 漏洩時の対応
安全管理措置を講じていても、情報漏洩は発生してしまう可能性があります。そのため、漏洩発生時に迅速かつ適切に対応できる体制を整備しておくことが求められます。
ガイダンスや法令では、以下の対応が求められています。
- 個人情報保護委員会への報告
漏洩が発生した場合、要配慮個人情報を含む事態や多数の本人に影響する事態などは報告義務の対象となります。 - 本人への通知
原則として、影響を受ける本人への通知が必要です。通知が困難な場合には、代替措置を講じることが認められています。 - 報告・通知の具体例
– 診療情報を含むUSBメモリの紛失
– 健康診断結果など要配慮個人情報の漏洩 - サイバーセキュリティ上の対応
サイバー攻撃やウイルス感染による漏洩が発生した場合、厚生労働省への連絡が求められるケースがあります。
これらの対応体制を事前に整備しておくことで、漏洩等発生時に迅速かつ適切な対応が可能となり、影響を最小限に抑え、患者や従業者の権利利益の保護と、医療機関の信頼維持につながります。
5.実務における情報漏洩対策の優先順位と具体策
漏洩時の対応を前提にしつつ、医療機関が日常的に実施すべき対策を優先順位を踏まえて整理すると、以下のようになります。
- アクセス権限の適切な設定と管理
個人情報へのアクセス権限を必要最小限に限定し、適切に管理するとともに、定期的な見直しを行います。 - 従業者教育の徹底
職員が個人情報保護の重要性を理解し、適切に取り扱えるよう、定期的に教育・研修を実施するとともに、取り扱いルールを周知徹底します。 - 事後対応の迅速化
ログが整備されていることで、情報漏洩発生時に関係者への対応や報告を迅速に行えます。規模や影響度に応じた適切な対応フローを構築するうえで、ログの存在は不可欠です。 - 監査体制の整備
個人情報取扱状況の監査を定期的に実施し、問題の早期発見と改善を行います。 - 委託先監督の強化
契約内容を明確化し、定期的な監査を通じて委託先の管理状況を確認するとともに、委託先が個人情報を適切に扱うよう監督体制を整備します。
6.監査や調査対応に備えた監査証跡と報告体制の整備
実務的な取り組みを支えるためには、監査証跡の記録や報告体制の整備が欠かせません。
- 監査証跡の記録・保存
個人情報の取扱い状況を記録し、適切に保存することで、監査や調査時に迅速な確認が可能になります。 - 報告体制の整備
漏洩事案や疑わしい事象が発生した際、速やかに上位管理者や監督官庁へ報告できる体制を整備します。
監査証跡と報告体制を組み合わせることで、透明性と説明責任を担保でき、組織としての信頼性も高まります。
7.まとめ
本コラムでは、医療業界における情報漏洩防止策を、事例・ガイダンス・実務の観点から整理しました。
医療機関にとって、情報漏洩防止は単なる法令遵守にとどまらず、患者との信頼関係を守るための中核的取り組みです。外部からの攻撃リスクだけでなく、内部的な管理不備や従業者の不適切な取り扱いも重要なリスク要因であることを、事例は示しています。
ルールやガイドラインを整備するだけでなく、現場で確実に運用される仕組みを作ることが欠かせません。アクセス制御、ログ管理、従業者教育、委託先監督など、基本的な施策を確実に実施することが、結果として患者の信頼維持につながります。
医療現場は日々多忙であり、すべての対策を完璧に実施することは容易ではありません。しかし、今回紹介した事例やガイドラインに沿った優先順位の整理、監査や報告体制の確立、職員教育の継続実施により、情報漏洩リスクを大幅に低減することが可能です。
患者情報を安全に管理することは、病院やクリニックの信頼維持に直結します。各医療機関は、自組織の実態に応じた情報漏洩防止策を整備し、日常業務に定着させることが求められます。
お問合せ
BlackBox Suiteは、多くの実績を持つ情報漏洩対策ソリューションです。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
利用用途やリスクに応じて、最適なご提案をいたします。