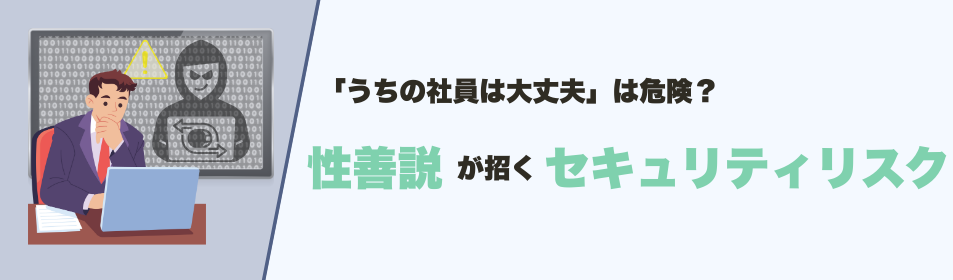コラム
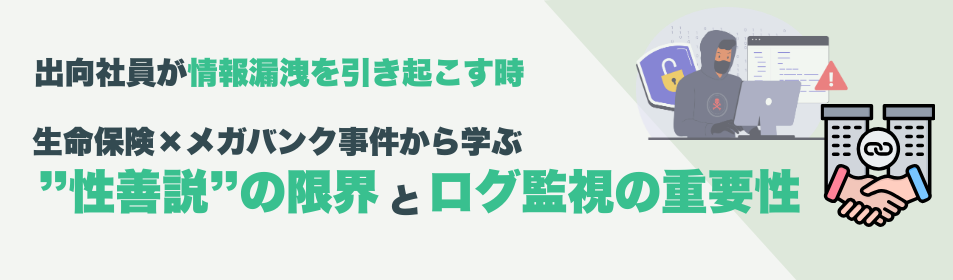
出向社員が情報漏洩を引き起こす時
——生命保険会社 × メガバンク事件から学ぶ”性善説”の限界とログ監視の重要性
あなたの会社では、出向社員やパートナー社員に対する情報アクセス権限の管理が徹底されていますか?
2025年7月、日本生命の出向社員が三菱UFJ銀行から社外秘資料を不正に持ち出し、社内で拡散していたというショッキングな事件が報じられました。表向きは信頼の上に成り立つパートナーシップ。しかし一度裏切りが起きれば、その代償は甚大です。
今回の事件は「性善説」に立った人事制度やアクセス設計が、情報漏洩リスクに対していかに脆弱であるかを露呈しました。
本コラムでは、本事件の詳細とともに、どのように情報漏洩が発生し、どこに監視の穴があったのかを深掘りします。さらに、「ログ管理」「アクセス監視」の実践的重要性と、企業が今後採るべき現実的対策について解説します。
※本コラムは、報道内容および弊社による独自分析に基づいて構成されています。内容の正確性については必ずしも保証されるものではありません。
目次
1.事件の概要と社会的インパクト
2025年7月15日、日本経済新聞および各報道機関は、日本生命の出向社員が、三菱UFJ銀行で入手した社外秘の内部資料を不正に持ち出し、自社(日本生命)内でメール転送・共有していたという事件を報じました。対象の資料は、三菱UFJ銀行が保有する保険商品の販売評価体系や営業戦略に関する詳細情報で、明確に「社外持ち出し禁止」の注意書きがあったにも関わらず、出向社員によって情報が複製・拡散されたとされています。
この報道は、保険業界だけでなく、銀行・証券などの金融業界全体を震撼させ、「出向社員」や「委託先社員」といった“外部人材”への情報アクセス権限管理の在り方に一石を投じました。

【出典】日経電子版 2025/7/15
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB159IY0V10C25A7000000/
2.漏洩された内部資料の中身と媒体
問題となった内部資料は、三菱UFJ銀行が2024年度に使用していた保険商品の販売戦略資料や営業評価基準の詳細でした。資料には、販売強化商品、評価指標、月次評価方法、販売インセンティブの仕組みなどが記載されており、同行の営業方針を知る上で極めて価値の高い情報です。
媒体はPDF形式の電子資料で、銀行の社内サーバに保管されていたものを、出向社員がメール添付により外部送信したとされています。この資料には明示的に「逆流厳禁」との注意書きがあり、銀行からの持ち出しが露見しないようにしていたようです。

3.情報流出のルートと拡散の実態
情報流出の経路は極めてシンプルであり、むしろその“簡単さ”に多くの企業が恐怖を感じたはずです。出向社員は三菱UFJ銀行内の共有フォルダから資料をダウンロードし、個人の業務用メールを使って日本生命の同僚宛に資料を送信しました。
その後、社内で資料が少なくとも270人に共有され、実質的に社内ポータルに近い状態で拡散されていたと見られています。この過程ではログ管理やアクセス制御が不十分であり、内部での監査やアラートも働いていませんでした。
アクセスログの取得から、リスク分析・検知、監査対応まで
—BlackBoxSuiteは、情報漏洩対策ソリューションです。

Webサイトに公開されていない資料をお
届けしています。
こんな方に最適な資料です。
4. 情報漏洩が発覚した理由と経緯
事件が表面化したのは、三菱UFJ銀行の社員が、同行が非公開としていた資料が日本生命内で多数人に共有されていることに気づいたことが発端とされています。資料の中には、銀行内部でしか知り得ない販売インセンティブ制度や営業方針に関する記述が含まれており、情報の出所を追跡する中で、出向社員がメールを使って資料を社外送信していた実態が判明しました。
その後、銀行側が日本生命に照会し、社内調査と報告を受けて正式に事件が確認された流れです。つまり、「偶然の内部告発」によって不正の全容が明らかになったという点において、企業としての予防策や早期検知体制の不備も改めて浮き彫りとなりました。
5.日本生命・三菱UFJ銀行の対応と波紋
報道後、日本生命と三菱UFJ銀行は共同で謝罪文を発表し、再発防止策の策定に乗り出すと表明しました。特に日本生命は、出向社員の情報リテラシー教育や持ち出し制限の見直しを進める一方で、再発防止委員会を立ち上げるとしました。
一方、三菱UFJ銀行側は、出向者に対する業務管理やモニタリング態勢の強化について必要な検討を行っていくことを強調しました。加えて、同銀行は今後「保険会社からの出向者の受け入れを停止する方針」を固めたと報じられ、再発防止に向けた姿勢を明確にしました。
6. なぜ性善説では防げなかったのか——モラルと犯罪心理の観点から
企業の多くは、人材管理や情報アクセスにおいて、基本的に「性善説」を前提に設計しています。「まさかこの人が裏切るはずはない」「情報を持ち出す意図などないはず」という信頼構造です。
しかし今回の事件は、まさに“善意の皮を被った”行為者による犯行であり、業務の一環としてのアクセスが“意図的”な情報漏洩に変わる瞬間を描き出しました。犯罪心理の観点から見ると、出向社員は「社のためになる」「評価される」といった動機で情報を持ち出した可能性も指摘されており、これは典型的な「モラルハザード」現象といえます。
7. 情報漏洩を防ぐ「ログ監視」と「アクセス監視」の再構築
こうした事件を防ぐには、「性善説」を前提とした体制から脱却し、常にアクセスログと行動を“見える化”する仕組みが求められます。
具体的には以下の対策が必要です:
- 出向社員・委託社員へのアクセス権限の段階的制御
- ログ管理ツールによるリアルタイムの操作監視
- ファイルダウンロード・メール添付のアラート設定
- AIによる異常行動検知(たとえば通常アクセスしない資料へのアクセス)
- 監査レポートの自動生成と月次分析
こうした「ログ監視」「アクセス監視」機能は、BlackBoxSuiteが得意とする領域であり、風評リスクの大きさと導入コストを比較すると、大手企業では早期の導入が求められるものです。
お問合せ
BlackBox Suiteは、多くの実績を持つ情報漏洩対策ソリューションです。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
利用用途やリスクに応じて、最適なご提案をいたします。