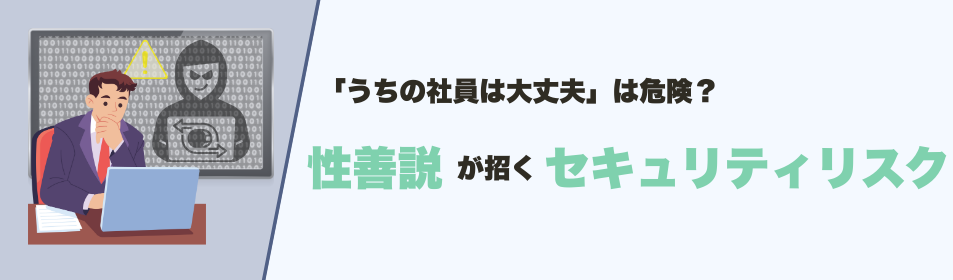コラム
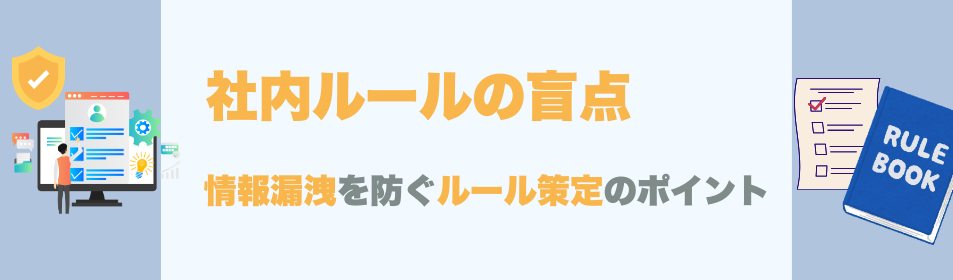
社内ルールの盲点 — 情報漏洩を防ぐルール策定のポイント
社内ルールは本当に機能しているのか?
企業における情報漏洩リスクは、セキュリティ意識の高い企業でも完全には排除できません。社内ルールやマニュアルを整備しても、実際の運用や従業員の行動次第では情報漏洩が発生することがあります。
皆さんの会社でも「ルールはあるけれど、現場で守られているか不安」という状況はありませんか。特にリモートワークが増えた現在、物理的に管理が難しい環境での情報取り扱いには注意が必要です。
本コラムでは、社内ルールの見落としやすい盲点と、情報漏洩リスクを下げるための具体的な策について解説します。
目次
1.社内ルールの盲点
企業における情報漏洩リスクは、セキュリティ意識の高い企業でも完全には排除できません。社内ルールやマニュアルを整備しても、実際の運用や従業員の行動次第では情報漏洩が発生することがあります。
たとえば、規程では「重要資料は社内サーバーに保存する」と定められていても、利便性を優先して個人のクラウドサービスに保存してしまうケースや、承認手続きを省略してデータを外部に送信してしまうケースも少なくありません。
社内ルールを策定する際に見落とされやすい盲点としては、以下のような点があります。
- 現場の実態に合わないルール
業務手順や現場の利便性を十分に考慮せずに作られたルールは、現場での運用が困難となり、結果的に例外対応や規程の形骸化リスクがあります。 - 部署や業務による適用の困難さ
全社員や全部署に同じルールを適用すると、特定の業務や部署ではルールを実務に沿って適用できない場合があり、運用上の齟齬が生じる可能性があります。 - 運用上の曖昧さ
誰がどの情報を扱うのか、どの範囲でルールが適用されるのかが明確でない場合、現場で判断が分かれ、意図せずルール違反が発生するリスクがあります。 - ルール見直しの不足
策定後に業務環境が変化してもルールが更新されない場合、現状に適合しない規程が残り、情報漏洩リスクが高まる可能性があります。 - 教育や啓発の不足
ルールを周知するだけでは不十分で、従業員が遵守する理由や背景を理解していなければ、意図せず違反してしまう可能性があります。
これらの盲点を認識することは、情報漏洩リスクを低減するためのルール策定・運用改善の第一歩です。ですが、本章で挙げた盲点からもわかるように、ルールだけでは防ぎきれないリスクも存在します。
そこで次章では、ルールでは防ぎきれないリスクと、それを補完する仕組みについて解説します。
2.ルールだけでは防ぎきれないリスク
前章を踏まえると、情報漏洩対策において「社員はルールを守るだろう」という性善説に基づく発想だけでは十分とは言えません。この前提で策定された規程は、実際の業務で簡単に破られてしまう可能性があります。
現実には、利便性や業務効率を優先して手順を省略したり、意図せず規程を破ってしまうケースも少なくありません。
こうした状況を前提にすると、社内ルールは情報漏洩対策において重要な基盤ではありますが、ルールだけでは防ぎきれないケースも少なからず存在します。そこで、ルールを補完する具体的な仕組みを併用することが有効です。
例えば、アクセスログの監査は、ルールを補完する運用の仕組みとして有効です。従業員のアクセス状況を可視化することで、不審なアクセスや潜在的なリスクを早期に検知でき、情報漏洩リスクの低減に役立ちます。
性悪説を前提とした、社内ルールの策定とあわせて、アクセスログ監査のようなルールを補完する仕組みを併用することは、リスク低減の観点から非常に有効です。
3.実効性のあるルール策定のポイント
前章で述べたように、ルールだけでは防ぎきれないリスクも存在します。しかし、ルールはリスク管理の基本的な土台です。
1章で整理した社内ルールの盲点を把握し、現場で機能するルールを策定することで、リスクを大幅に低減させることが可能です。
ここでは、現場で守られるルールを作るための具体的な策定ポイントを解説します。
- 業務実態に即したルール
現場の業務フローから乖離したルールは、形だけ整っていても守られません。ヒアリングや実態調査を踏まえて、現場に無理なく適用できる形にすることが大切です。 - 曖昧さを排除すること
「適切に」「必要に応じて」といった曖昧な表現は解釈の余地を生み、守られない原因となります。具体的な基準や手順を明確に記すことが求められます。 - 部門別・業務別にカスタマイズする
全社共通の基本ルールと、部門や業務ごとの特有ルールを分けて設計することで、現場の実態に即した柔軟な運用が可能になります。これにより、特定の業務や部署でルールを無理に適用する必要がなくなり、遵守率の向上にもつながります。 - 利便性と運用負荷を考慮する
ルールが現場の作業効率を大幅に損なったり、管理部門や現場に過度な負担を強いる場合、守られにくく長続きしません。利便性とセキュリティ確保のバランスを取りつつ、可能な限りシステムや仕組みで運用を支援することで、持続可能なルール運用が可能になります。
4. 社員教育と継続的なルール改善
3章で策定したルールを現場で機能させるためには、社員教育やヒアリング、定期的な見直しが不可欠です。
社員がルールの目的や背景を理解し、日常業務に沿って運用できるようにすることが重要です。また、現場の声を取り入れ、状況に応じてルールを柔軟に見直すことで、実効性を高めることができます。
これらを実現するための具体的なポイントは、次の通りです。
- 教育と周知の重要性
ルールの背景や遵守する理由を従業員が理解していなければ、意図せず違反してしまう可能性があります。定期的な研修や周知活動により、従業員の理解度と意識を高めることが重要です。 - 現場からのフィードバック
実務に沿ったルール運用を維持するためには、現場からのヒアリングや意見収集が役立ちます。現状の課題や改善点を把握し、ルールの精度向上に反映させることができます。 - 定期的な見直し
業務環境の変化や新しいリスクへの対応を考慮し、ルールを定期的に更新することが必要です。見直しのプロセスを定常化することで、ルールが形骸化することを防ぎ、情報漏洩リスクを継続的に低減できます。
5.社内ルールを補完する仕組み
どんなに練られたルールも、人が運用する以上、逸脱の可能性はゼロになりません。また、ルールの範囲内に見える行為であっても、意図的に不正を行う従業員や外部関係者による悪意のある行為が発生する可能性があります。
こうしたリスクに対応するためには、2章で解説したように、社内ルールを補完する仕組みが重要です。アクセスログ監査などの仕組みを併用することで、潜在的なリスクや不正の兆候を早期に把握し、迅速に対応することが可能となります。
- アクセスログ監査
誰が、いつ、どのデータにアクセスしたかを記録・分析することで、ルール遵守状況を「可視化」できます。 - アラートの自動化
通常ではあり得ない操作(深夜のアクセス、大量のデータコピーなど)を自動検知し、迅速に対応できます。 - 監査結果のフィードバック
監査で得た情報をルール改善や教育に活用することで、ルールと監査のサイクルが完成します。
弊社BlackBoxSuiteでは、アクセスログの記録やリスク分析、監視、不審なアクセスに対するアラート機能を提供しており、社内ルールを補完する運用を支援します。システムによる自動監査により、人的負担を減らしつつ、リスク低減の効果を高めることが可能です。
BlackBoxSuiteは、社内ルールを補完する運用を支援します。

Webサイトに公開されていない資料をお
届けしています。
こんな方に最適な資料です。
6.まとめ
本コラムでは、社内ルールの盲点とルール策定のポイント、さらにルールだけでは防ぎきれないリスクやそのリスクを低減するための具体的な策について解説しました。
ポイントをまとめると以下の通りです。
- 社内ルールには盲点が存在し、現場の実態に合わない場合や曖昧なルール、部署・業務による適用困難さ、教育・見直し不足などがリスクにつながります。
- ルールだけでは防ぎきれないリスクがあるため、補完する仕組みと併用することが有効です。
- ルール策定では、現場に即した内容、曖昧さの排除、部門・業務別のカスタマイズ、利便性と負荷のバランスを意識することが重要です。
- 教育・周知や現場フィードバック、定期的な見直しといった運用面を強化することで、ルールを現場で機能させることができます。
- システムやツールの活用により、人的負担を軽減しつつ、ルールを補完する運用が可能です。
社内ルールは、ただ「ある」だけでは意味がありません。現場で機能し、潜在的リスクや不正に対応できる形で運用することが、情報漏洩リスクを低減するための最も重要なポイントです。
お問合せ
BlackBox Suiteは、多くの実績を持つ情報漏洩対策ソリューションです。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
利用用途やリスクに応じて、最適なご提案をいたします。