コラム
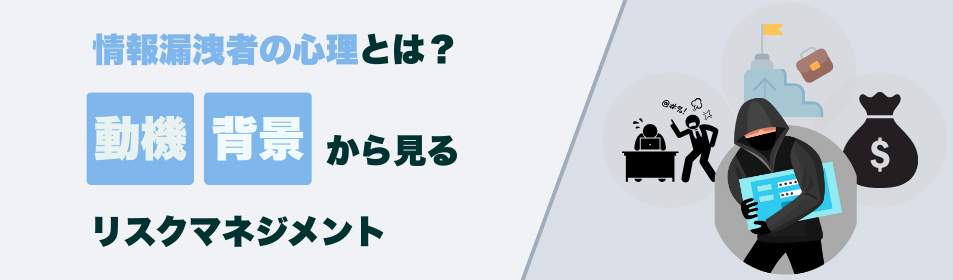
情報漏洩者の心理とは?動機・背景から見るリスクマネジメント
近年、企業や組織における情報漏洩事件は後を絶ちません。特に外部からのサイバー攻撃だけでなく、内部関係者による不正行為が大きなリスクとして認識されつつあります。
内部不正は、従業員や元従業員といった「組織の内部」を知る人物が関与するため、発覚が遅れたり被害が拡大したりする傾向があります。IPA(情報処理推進機構)も「組織における内部不正防止ガイドライン」を公開し、組織が取るべき対策を整理しています。
内部不正は心理的要因や職場環境、監視体制の不備などが複雑に絡み合って発生するため、単なる規則や技術対策だけでは十分に防げない場合もあります。
本コラムでは、内部不正防止ガイドラインをもとに、内部不正が生じる背景やその兆候、組織が取り得る対策について考察します。
目次
1.情報漏洩と心理要因の関係
情報漏洩は外部からの攻撃や不正アクセスに限らず、組織内部から発生するケースも少なくありません。IPA(情報処理推進機構)が発表する「情報セキュリティ10大脅威 2025」においても、「内部不正による情報漏えい等」が上位に位置付けられており、長年にわたり大きなリスクとして注目されています。内部不正は、正規の権限を持つ従業員や委託先関係者が関与することが多く、既存の技術的な防御策だけでは発見や抑止が難しい場合があります。
内部不正を考えるうえで重要なのが「心理的要因」です。人は何らかの心理的背景や動機を抱えて行動します。経済的困窮、職場への不満、評価されないことへの苛立ち、自己顕示欲などが、不正の引き金になることがあります。心理的要因を理解することは、単なる規則やシステム制御だけでは防ぎきれない「人間由来のリスク」に備えるための出発点となります。
また、心理的要因は単独で作用する場合もあれば、組織文化や上司との関係性、職務の特性などと絡み合って複雑化することもあります。したがって、内部不正のリスク分析には、心理面と組織面の両方を包括的に捉える視点が必要です。

出典:情報処理推進機構(IPA)情報セキュリティ10大脅威 2025
2.内部不正防止ガイドラインが示す視点
IPAが公開する「組織における内部不正防止ガイドライン」では、内部不正のリスクを多面的に捉える重要性が示されています。内部不正の要因は「心理的要因」「組織的要因」「技術的要因」に分類され、どれか一つの視点だけでは不十分で、包括的な対策が推奨されています。
心理的要因としては、職務上の不満や人間関係、経済的事情などが不正の引き金になり得ることが整理されています。付録Ⅰの「内部不正事例集」では、実際に発生した事例が具体的に紹介され、どのような心理的背景が行動に結びついたのかを理解できる資料になっています。
このガイドラインは、単なる理論ではなく、組織が具体的に対策を検討する際の参考資料として活用できます。心理的要因や行動の兆候を把握することが、内部不正リスク低減の第一歩です。
3.事例にみる内部不正の心理と動機
前章で触れたように付録Ⅰの事例集には、内部不正に至る心理的背景や動機が具体的に示されています。これらの事例を整理すると、共通して見られる心理パターンや行動の傾向が浮かび上がります。
以下に代表的なパターンを紹介します。
- 組織への不満や報復心理
評価や昇進への不満から、退職時に機密情報を持ち出すケースがあります。心理的には「自分を正当に評価してもらえなかった」「組織に仕返ししたい」という感情が行動を正当化する要因になっています。 - 承認欲求や自己顕示欲
技術力を誇示したい、周囲から注目されたい心理から、不正アクセスやデータの不正利用を行う場合もあります。自己の能力を示すことで満足感を得る行動です。 - 退職や転職に伴う持ち出し
退職や転職時に、業務上知り得た情報を新しい職場で活用するために持ち出すケースもあります。動機は「自己のキャリアを有利に進めたい」という合理的打算であることが多く、組織にとっては深刻なリスクとなります - 経済的困窮による動機
従業員が個人的な借金返済のため、顧客情報を持ち出し売却したケースがあります。この場合、心理には「切迫感」や「早急に金銭を得たい」という焦燥感が働いており、生活状況が不正の直接的な動因となっています。
これらの事例から、情報漏洩の背景には単なる規則違反ではなく、人間の感情や心理が深く関与していることがわかります。

出典:情報処理推進機構(IPA)内部不正による情報セキュリティインシデント実態調査-調査報告書-
4. 不正が起きにくい職場環境の条件
心理的要因を考慮すると、不正を未然に防ぐためには職場環境の整備が重要です。ガイドラインでも示されているポイントは以下の通りです。
- 透明性のある評価制度
評価や昇進のプロセスを明確にし、不公平感を減らすことで不満が蓄積しにくくなります。 - 相談しやすい環境
困難やストレスを抱える従業員が孤立すると不正のリスクが高まります。相談窓口やメンタルサポートの整備が有効です。 - 心理的安全性のある文化
意見や不満を率直に表明できる文化は、不満や不信感を内部不正につながる前に解消する役割を果たします。 - 業務分散と権限管理の適正化
一人に権限が集中すると不正の余地が増えます。業務を適切に分散し、権限を明確化するとともに、複数人によるチェックを導入することが重要です。
このように、心理的負荷を軽減する環境づくりは、不正の芽を早期に摘むための有効な手段となります。
5.心理的要因に基づくリスクマネジメントのアプローチ
心理的要因を踏まえたリスクマネジメントには、教育・兆候把握・リスク評価など複数のアプローチがあります。部隊的には以下の通りです。
- 教育と啓発
内部不正の事例や被害の大きさを従業員に伝えることで、自らの行動を見直すきっかけを提供します。心理的な不満や動機が不正に結びつく前に認識を促すことが重要です。 - 早期兆候の把握
急な残業増加や職場での孤立、権限を逸脱した行動など、不正の可能性がある兆候をモニタリングします。これにより、心理的要因によるリスクを技術的に補完できます。 - 定期的なリスク評価
心理的・組織的・技術的要因を含め、内部不正リスクを定期的に棚卸しし、改善点を明確化します。評価の際には、業務の分散や権限の明確化も含め、権限集中による不正リスクを低減する仕組みを検討することが推奨されます。
心理面の理解を組織的に反映させ、教育や評価、監査と組み合わせることで、内部不正リスクの低減に寄与します。
6.ログ監査と可視化が果たす役割
心理的要因を理解することは内部不正リスクの把握に不可欠ですが、どれだけ理解しても不正を完全に防ぎきることは難しい場合があります。そのため、具体的な行動の証跡を把握することも重要です。内部不正は正規の権限を利用して行われることが多く、アクセスログやデータ利用状況の可視化が役立ちます。
弊社BlackBoxSuiteは、ユーザーごとのアクセス履歴を詳細に収集・保存し、不審な行動の兆候を早期に発見できるソリューションです。心理的背景を理解したうえで、実際の行動を把握・監査することで、リスクマネジメントの精度を高めます。
例えば、通常業務で不要な顧客データへのアクセスが増えている場合、心理的要因に基づく不正の可能性を早期に察知できます。技術と心理の両面からの対策が、より実効性のある防止策につながります。
BlackBoxSuiteはアクセスログの取得・分析を通じて、
不正の兆候を早期に検知します。

Webサイトに公開されていない資料をお
届けしています。
こんな方に最適な資料です。
7.まとめ
情報漏洩の背後には必ず人間の心理が存在します。経済的困窮、職場への不満、承認欲求、キャリア上の打算など、多様な動機が不正行為に影響を与えます。IPAの「組織における内部不正防止ガイドライン」でも、心理的要因を理解することが内部不正防止の重要な柱であると示されています。
組織は、不正が起きにくい職場環境を整え、心理的要因を軽視せずにリスクマネジメントを行うことが求められます。そのうえで、ログ監査やデータ利用状況の可視化などの技術的対策を組み合わせることで、より強固な情報漏洩防止体制を築くことができます。
内部不正対策は、心理面・組織面・技術面のバランスを意識して取り組むことで、初めて十分な効果が期待できるといえます。
出典
- IPA(情報処理推進機構)「組織における内部不正防止ガイドライン」
https://www.ipa.go.jp/security/guide/insider.html - IPA(情報処理推進機構)「内部不正による情報セキュリティインシデント実態調査」報告書について
https://www.ipa.go.jp/archive/security/reports/economics/insider.html - IPA(情報処理推進機構)「情報セキュリティ10大脅威」
https://www.ipa.go.jp/security/10threats/index.html
お問合せ
BlackBox Suiteは、多くの実績を持つ情報漏洩対策ソリューションです。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
利用用途やリスクに応じて、最適なご提案をいたします。