コラム
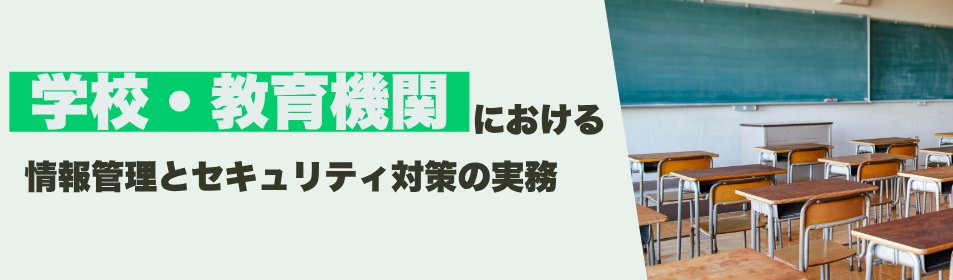
学校・教育機関における情報管理とセキュリティ対策の実務
教育機関では、児童生徒や保護者、教職員など、多様な立場の個人情報が日々取り扱われています。成績情報や健康情報、家庭の状況など、教育活動に必要な情報は多岐にわたりますが、それらが一度外部に漏えいすると、本人の権利侵害や信頼失墜といった重大な結果を招くおそれがあります。
近年、USBメモリやクラウドサービスの誤使用、メール誤送信など、学校現場における情報漏えい事案が継続的に報告されています。こうした状況を踏まえ、個人情報保護委員会や文部科学省は、教育機関における情報管理やセキュリティポリシーのあり方について具体的な指針を示しています。
本コラムでは、個人情報保護委員会や文部科学省の資料に基づき、学校現場で生じやすい個人情報漏えいの原因とその傾向を整理します。また、具体的な留意点や教育情報セキュリティポリシーの基本理念・対策基準を確認し、現場で実効性のある運用や継続的な監査・改善サイクルの構築の重要性についても解説します。
目次
1.教育機関における個人情報管理の重要性
教育機関が保有する情報は、単なる個人データにとどまりません。成績や出欠、健康状態、家庭の経済状況など、極めてセンシティブな内容を含むものが多く、漏えいした場合には、個人の尊厳を損なうリスクがあります。
個人情報保護法においても、学校法人や地方公共団体の教育委員会等は「個人情報取扱事業者等」として適用対象となり、適正な管理と安全確保措置を講じる責任があります。とりわけ、情報通信技術(ICT)の活用が進む中で、教育データのデジタル化が急速に進展しており、紙媒体とは異なる新たなリスクへの対応が求められています。
こうした背景から、国は教育機関に対し、ガイドラインや留意事項を通じて、具体的な情報管理体制の整備を促しています。
2.教育現場で多発する典型的な情報漏えいの原因
個人情報保護委員会の分析結果によると、教育機関での漏えい原因として以下のような傾向が見られます。
- 紛失
– 持ち出した個人情報の紙媒体を紛失
– USBメモリ等の電子媒体の紛失 - 誤交付・誤送信
– 個人情報が記載された資料を、誤って別の生徒や保護者に交付
– メールやオンラインツールで誤った宛先に送信 - ICTツール等の操作ミス
– ICTツールやクラウドサービスの操作ミスによる情報漏えい
– 共有範囲の誤設定により、生徒や保護者以外に情報が見える状態となった - 管理不十分
– 紙媒体やUSBメモリ等の電子媒体の紛失や置き忘れ
– 資料等の保存・整理が不十分の状態での業務による誤交付等
– 廃棄してはいけない書類を誤って廃棄 - 人的要因(教育・認識不足等)
– 個人情報の取り扱いに関する理解不足により、誤操作が発生
– 事務処理や連絡時に必要のない個人情報まで含めて送信 - 関係者の不正目的による漏えい
– 退職時に生徒のデータを不正に持ち出し
これらは、多くの場合「ヒューマンエラー」として扱われますが、根本には管理体制や運用ルールの不徹底が存在します。したがって、個人の注意だけに頼るのではなく、システム的・組織的にリスクを低減する取り組みが求められます。

出典:個人情報保護委員会
学校における個人情報の漏えい等事案を踏まえた個人情報の取扱いに関する留意点について
3.個人情報保護委員会が示す「個人情報の取扱いに関する留意点」の概要
個人情報保護委員会が教育委員会等の学校設置者や教職員向けに公表した「学校における個人情報の漏えい等事案を踏まえた個人情報の取扱いに関する留意点について」は、過去に教育機関から受領した報告をもとに、学校現場で生じやすい個人情報漏えい等事案についてまとめたものです。
資料では、漏えい等事案が発生しやすい状況を整理し、その発生原因や再発防止策について示されています。これにより、日常の業務における生徒の個人情報の取扱いや、ルール・対策の見直しに役立てることができます。
資料に記載されている主な留意点は以下の通りです。
- 外部記録媒体の使用・管理
– USBメモリの保管・管理は、校長及び教頭等の管理者が厳重に行う
– 外部記録媒体の使用は承認制または禁止とする - デジタルツール等の利用時の確認
– ツール利用時の校内マニュアルを作成し、教職員に研修を実施
– 権限や公開範囲の定期的な見直し - 誤送信・誤交付の防止
– メール送信時の宛先・添付ファイル確認の徹底
– 書類と宛先の突合作業の実施 - 漏えい発生時の対応体制
– 事実確認、原因究明、再発防止策の検討
– 報告体制の整備 - セキュリティー教育の実施
– 教職員や生徒に対する情報リテラシー、モラル教育等の実施
– セキュリティ意識向上のための研修の実施
この資料を活用することで、教育現場での個人情報管理に関する理解を深め、日常業務での情報取扱に関するルール・対策の見直しに役立てることができます。
4. 文部科学省「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」の要点
文部科学省が公表している「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」は、教育情報セキュリティポリシーの基本理念と、教育委員会や学校が対策を検討する際の考え方について整理した資料です。本ガイドラインでは、教育委員会や学校設置者を対象としており、基本理念に基づいた対策基準の例が示されています。
以下は、教育情報セキュリティポリシーにおける基本理念です。これらは、教育委員会や学校が情報セキュリティ対策を検討・実施する際の指針となります。
- 組織体制を確立すること
- 児童生徒による重要性が高い情報へのアクセスリスクへの対応を行うこと
- 標的型及び不特定多数を対象とした攻撃等による脅威への対応を行うこと
- 教育現場の実態を踏まえた情報セキュリティ対策を確立させること
- 教職員の情報セキュリティに関する意識の醸成を図ること
- 教職員の業務負担軽減及びICTを活用した多様な学習の実現を図ること
- 児童生徒の情報セキュリティ・情報モラルに関する意識の醸成を図ること
基本理念を踏まえたうえで、次に具体的な対策基準の一部を紹介します。
- 組織体制の整備
情報セキュリティ対策を確実に行うためには、組織体制を整備し、一元的にセキュリティ対策を実施することが必要です。そのため、情報組織体制を構成する責任者や設置すべき組織、それらの役割について定められています。 - 情報資産の分類と管理方法
情報資産を適切に守るためには、情報資産をその重要性に応じて分類・仕分けし、その分類に応じた管理を行う必要があります。そこで、情報資産の重要性やアクセスする主体に基づく分類・仕分けの考え方と、その分類に応じた管理方法について定められています。 - 人的セキュリティの確保
様々な立場の人が情報資産を取り扱うという特徴を持つ教育現場では、教職員等のルール遵守を徹底させるとともに、教育現場での事故事例等を踏まえた研修の実施や、教育情報セキュリティ管理者(校長)からの働きかけ、児童生徒への指導等を通じて、一人ひとりに遵守すべき内容とその必要性を浸透させることが重要です。そのため、教育情報セキュリティ管理者(校長)・教職員等・教育委員会の遵守事項を定めるとともに、研修・訓練、情報セキュリティインシデントの連絡体制の整備についても定めています。 - 技術的セキュリティ
ネットワークや情報システム等の設定管理が不十分な場合、不正利用による情報システム等へのサイバー攻撃、情報漏えい、損傷、改ざん、重要情報の詐取、内部不正等の被害が生じるおそれがあります。そこで、情報システム等の不正利用を防止し、また不正利用に対する証拠の保全をするために、コンピュータ及びネットワークの設定管理やアクセス制御に関する規定、不正プログラムや不正アクセスに対する対策などを定めています。
このように、教育情報セキュリティポリシーでは、基本理念に基いた対策基準が定められています。これらを踏まえて具体的な対策を実施することで、学校における情報セキュリティの確保が図られます。
5. 実効性あるセキュリティポリシーと運用体制の構築
組織的に情報セキュリティを確保するには、ガイドラインで定められた各種対策や管理体制に加え、適切な運用が求められます。教職員による教育ICTの活用や、児童生徒による1人1台端末・クラウドの安全な利用を見据え、各自治体・学校は、実現したい環境と情報セキュリティのバランスを考慮して運用規定を整備する必要があります。
教育情報セキュリティポリシーに関するガイドラインでは、主に以下の点が定められています。
- 情報システムの監視対策
不正プログラムや不正アクセス、教職員による不正利用などから情報システムを守るため、アクセスログの取得や不正アクセス検知などの監視方法が定められています。 - ドキュメントの管理
情報セキュリティ対策の詳細を記載したドキュメントは機密事項に相当するため、外部への漏えいを防ぎ、攻撃者の手に渡らないように、システム仕様書や運用管理記録、設定情報などの文書を適切に管理し、必要に応じて確認・保管する方法が規定されています。 - ID・パスワードの管理
教職員や生徒のID・パスワードの発行・変更・削除、利用権限の付与・管理など、安全な運用方法が定められています。 - 管理者権限の管理
クラウドサービスやサーバの全機能を利用できる特権IDは限られた利用者にのみ付与するなど、管理手続きが規定されています。 - ポリシー遵守状況の確認・管理
教育情報セキュリティポリシーの遵守状況を確認する体制を整備し、問題があった場合の対応方法が定められています。 - 懲戒処分等の規定
教職員等がポリシーに違反した場合の懲戒処分及び手続きが規定され、違反の未然防止に一定の効果が期待されます。 - セキュリティ侵害事案発生時の対応
情報セキュリティインシデントやシステムの欠陥・誤動作、ポリシー違反によるセキュリティ侵害事案が発生した場合に、被害の拡大防止や迅速な復旧を行うため、緊急時対応計画の策定が規定されています。
このほかにも、外部専門家の支援体制や法令遵守に関する規定等が定められています。各自治体・学校は、これらの規定を踏まえて、教職員や児童生徒が安心してICTを活用できる環境を整備することが重要です。適切な運用規定の整備と定期的な見直しにより、情報セキュリティの維持・向上が期待できます。
BlackBoxSuiteでは、アクセスログを取得し、
不審なアクセスを検知することが可能です。

Webサイトに公開されていない資料をお
届けしています。
こんな方に最適な資料です。
6.継続的な監査と改善サイクルの確立
情報セキュリティ対策は、一度整備すれば完了ではなく、実施状況の評価と改善を繰り返すことで維持・向上が図られます。各自治体や学校では、監査や自己点検を通じて、情報セキュリティポリシーの遵守状況や運用の実効性を確認することが求められます。
- 監査の実施
専門知識を持ち独立性のある者が行い、教育情報システムやネットワーク、外部委託事業者の情報管理状況を定期的に評価します。監査結果は改善指示やフォローアップを通じて対策に反映されます。 - 自己点検の実施
教職員や管理者が自らの業務や権限の範囲で定期的に行います。監査ほどの客観性はないものの、組織全体のセキュリティ対策の改善や教職員等の意識向上に有効です。 - 結果の活用と改善サイクルの確立
監査や自己点検の結果は、各主体の業務改善や教育情報セキュリティポリシー・関係規程の見直しに活用します。情報セキュリティの脅威や技術の変化が確認された場合は、ポリシーや規程を見直し、環境の変化に柔軟に対応することが重要です。
このような継続的な評価・改善のサイクルにより、教職員や児童生徒が安心してICTを活用できる環境を維持することができます。
7.まとめ ― 安全で信頼される教育情報環境の実現へ
教育現場における情報管理とセキュリティ対策は、単なるルール策定にとどまらず、日常業務での実効性が重要です。学校や教育機関では、児童生徒や保護者の個人情報を適切に管理することが、教育活動の信頼性や児童生徒の権利保護に直結します。
本コラムで整理したように、教育現場で発生する情報漏えいの原因は、紛失や誤送信、操作ミス、管理不十分、人的要因、さらには不正目的による持ち出しなど多岐にわたります。これらを未然に防ぐには、個々の注意に頼るだけでなく、組織的・システム的な対策が不可欠です。
個人情報保護委員会の留意点や文部科学省の教育情報セキュリティポリシーでは、外部記録媒体の管理やデジタルツール利用時の確認、誤送信・誤交付の防止、セキュリティ教育の実施など、具体的な管理・運用方法が示されています。さらに、実効性ある運用規定の整備や定期的な監査・自己点検を通じて、情報セキュリティの維持・向上を図ることが求められます。
教育機関は、組織的な体制や責任の明確化、情報資産の適切な管理、教職員や児童生徒への研修・教育、ID・パスワードや権限管理、システム設定の維持、アクセスログの取得、緊急時対応計画の策定など、さまざまな対策を実務に落とし込むことが重要です。また、監査や自己点検の結果を活用し、ポリシーや規程を見直すことで、環境変化や新たな脅威に柔軟に対応できます。
これらを総合的に実施することで、児童生徒や保護者が安心して教育活動に参加できる、安全で信頼される教育情報環境の実現が可能となります。
出典・参考情報(2025年10月時点)
- 個人情報保護委員会
学校における個人情報の漏えい等事案を踏まえた個人情報の取扱いに関する留意点について
https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/250625_alert_school/ - 文部科学省
「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」公表について
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1397369.htm
お問合せ
BlackBox Suiteは、多くの実績を持つ情報漏洩対策ソリューションです。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
利用用途やリスクに応じて、最適なご提案をいたします。